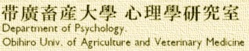 卒業論文の書き方
卒業論文の書き方
2009年12月26日 渡邊芳之 1年半やってきた卒業研究の総まとめとして,研究の内容を卒業論文にまとめます。努力すれば努力するほど自分も満足しますし一生の思い出にもなりますので,ぜひ一生懸命書いてみてください。 1.論文の書式と構成論文はA4用紙を縦に使い,横書きで執筆します。原則としてワープロで作成し,1ページの文字数は少なめ(25字×32行で1ページ800字,30字×40行なら1ページ1200字,それ以上つめ込んではダメ)にし,四方に十分な余白を取ります。ページの下には必ず頁番(ページ数)を記入します。章が変わる時にはかならず改ページをします。でき上がった論文は生協に売っている縦綴じのファイルに綴じて提出します。論文の表紙とは別に,ファイルの表にも論文タイトルと学籍番号,名前等を書きます。 論文は以下のような章構成で執筆します。各章の中でも1),2)とか第1節,第2節とかできるだけ細かく小見出しをつけていきます。
もし研究全体の中が細かく2つまたは3つの研究に別れる場合には,以下のような構成をとることができます。
論文の要約は他の章が全部書き終わってから,それら全体を要約して書きます。一般的には用紙1ページ分くらいでまとめます(所属ユニットによっては指定の字数がある場合があります)。その他,研究の内容や結果に応じて柔軟に変更することも可能ですので,必要に応じて指導教員に相談してください。論文の書式や構成について細かいことについては「日本心理学会 執筆・投稿の手引き」が参考になります。 2.図表と目次論文の中に図表を挿入する時は,原則としてその図表について述べている本文ページの近くに図表だけで1ページを使って挿入します。1ページに複数の図表を入れることはかまいませんが,本文と図表が同じページの中にあることは避けます。図表には必ず番号とタイトルをつけます。図(絵や写真,グラフ)のタイトルと番号は図の下につけます。表(文字と数字,記号だけで構成されるもの)のタイトルと番号は表の上につけます。図表の番号は図と表を別々に,図は「図1」から通し番号を,表は「表1」から通し番号を,論文全体にわたってつけます。論文全体に図が21個,表が17個あるなら,図は図1から図21まで,表は表1から表17までの番号がつくことになります。 目次は要約のすぐ後につけます。目次には本文の章,節(小見出し)のページ数を示します。Wordの目次機能を使うと簡単に作成することができます。本文の目次のほかに図表の目次もつけます。図は図,表は表それぞれで,図表番号とタイトル,ページを示します。 3.序論序論では,どうしてこの研究を,このやり方で行うのか,そのことにどういう意味があるのかを読者に伝えることをめざします。けっこう書くことは多いので,最低でも10ページ(原稿用紙20-30枚)くらいにはなります。 1)「序論の序論」序論の冒頭は「最近世の中ではこれこれこうなっている」とか「自分は以前こんな経験をした」とか,研究に関係のある一般的な事柄から書き始め,だんだん研究のテーマへと近づけていきます。ここでは,自分がやった研究と世の中の動きや,自分自身の興味とのつながりを書き,自分の研究が単なる「研究のための研究」でないことを示すことが大切です。この部分が最低2ページ。2)研究史や研究のレビュー自分が研究したテーマや関連するテーマで,これまでどんな研究や分析が行われてきたのか(先行研究),それらの成果は何だったのかをレビューします。できるだけたくさんの研究や文献を引用して,そのテーマの研究全体の歴史がわかるようにします。この部分が最低6ページ。誰が何をやった,と書く場合には必ずその文献を示します。以下は文献の示し方の例。渡邊(2005)は,遺伝と環境に関する心理学の論争を「変わるものと変わらないもの」の対比として示した。渡邊によると,変わらないものを指向する研究は予測を重視し,変わるものを指向する研究は制御を重視したことが特徴である。 心理学における遺伝と環境の論争では,遺伝子型と表現型とを区別する現代遺伝学の考え方はあまり理解されず,遺伝決定論に陥りやすいことが問題である(渡邊,2005; Cosmides, 1992)。文献の示し方の決まりについても「日本心理学会 執筆・投稿の手引き」が参考になります。引用した文献はかならず論文末尾の「引用文献」にリストアップされている必要があります。 3)この研究はなにをめざすのか上の研究レビューをもとに,これまでの研究ではなにがわかったのか,なにがわかっていないのかを明らかにした上で,そのわかっていない部分のうち,自分はこの研究でなにをどのように調べようとしているのか,その理由は何か,ということを述べます。この部分が最低2ページ。4.目的この章では,この研究がなにを,どのように明らかにしようとしているのかを簡潔に述べます。基本は「本研究では,〜を〜するために〜を行い,〜を〜することを目的とする。そのために〜を〜するとともに,〜についても〜する。」みたいな文章になります。この章は場合によっては1ページに収まってしまうかもしれません。研究が「研究1」「研究2」のように分割される場合には,ここでは研究1と研究2の全体を通じてなにをどのように明らかにしようとしているのか書きます。たとえば「本研究では〜を〜するために,研究1では〜を〜することによって〜を〜し,研究2では〜を〜して〜する。研究1と研究2の結果を総合して,〜の〜について検討していく」みたいに書きます。 5.方法研究をどのような方法で行ったのかについて詳細に書きます。「自分と同じ程度の知識と能力を持った人であれば,この論文の方法の章を読んだだけで自分と同じ研究を追試できるように書く」ことが原則です。そのために,研究に用いた材料,器具や道具,調査やインタビューの方法などについて詳しく書いていきます。質問紙調査を行った場合には質問紙の作成方法,そのために用いた文献や論文,質問項目,質問紙の構成などについて書くとともに,質問紙の実物を論文末尾に付録としてつけて,文中で参照します。「研究1」「研究2」がある場合には,研究1の章で研究1の方法,研究2の章で研究2の方法を述べます。ページ数は研究の内容によりますが最低4ページくらいは必要だと思います。 6.結果「方法」の章で書いた方法で研究を行った結果として得られたデータやそのデータの分析について書いていきます。書くことや書き方は研究の内容によって違います。 1)観察の場合観察の結果得られたデータについて述べていきます。何回かの観察を行った場合には,観察の日時や内容ごとに観察結果をまとめた上で,それぞれの観察でわかったことを述べていきます。そのうえで,それらの観察全体を集計したり比較検討したりして分析を進めていきます。2)インタビューの場合インタビューで得られたデータ(インタビューで対象者が話したこと)について述べていきます。インタビューの対象者についての情報,インタビューの日時や場所についても詳しく記載します。インタビューの文字起こしの中から特徴的な発言を抜き出し,それについての自分のコメントを書いていきます。複数のインタビューを行った場合はそれらを相互に比較検討します。3)実験の場合実験データを示します。まず得られたデータの基礎統計を示した上で,分散分析などの統計分析結果を述べます。複数の実験を行った場合にはその結果を集計したり,比較検討したりして分析します。4)調査の場合調査によって得られたデータについて述べます。まず調査のすべての項目についての基礎統計を示します。カテゴリーの場合は度数分布表を,評定尺度の場合は平均値,標準偏差を示します。そのうえでクロス統計と検定,差の検定,分散分析や因子分析などを行った結果と,それぞれの結果から何がわかるかについて述べます。いずれの場合も,図表をふんだんに使って,得られたデータをできるだけ完全に記述するよう心がけてください。研究内容にもよりますがどんな場合もこの章は必ず10ページ以上になるはずです。 7.考察この章では,研究の結果から何がわかり,何がわからなかったか,今後の研究の課題は何かといったことを書いていきます。章全体で最低6ページ。 1)結果の要約1〜2ページを使って,「結果」の章に示された研究結果を,特に重要なものを中心にまとめます。2)わかったこと研究結果からわかったことを整理していきます。それらが先行研究と関係している場合は先行研究を引用した上で,先行研究の結果とこの研究の結果がどこが共通していて,どこが違うのかについて述べます。そして,この研究を行ったことにどのような意義があったのかを考えます。3)わからなかったことと今後の課題最後に,自分としては知りたかったけれどこの研究ではわからなかったことについて述べます。わからなかった理由が研究の欠陥や失敗による場合にはそれについても正直に書きます。,そのうえで,今後このテーマの研究にどのような課題があるか,どんなことが求められるかについて展望します。8.文献と付録その他論文の本文が終わった後に「引用文献」「付録」などをつけます。 1)引用文献論文中に引用したすべての文献や論文のリストを作成します。リストの書式は細かく決まっていますので「日本心理学会 執筆・投稿の手引き」を参照してください。原則として,本文中で引用された文献はすべてここにリストアップされていなければなりませんし,ここにリストアップされる文献はすべて本文中で引用されていなければなりません。2)付録研究内容と関係があるが,量が多すぎて本文中に図表などで入れることができなかったものを付録としてつけることができます。たとえば質問紙調査の質問紙,インタビューの文字起こしそのもの(必要な場合のみ),観察データの書き起こしなどです。付録といっても雑誌の付録みたいにただつければよいのではなく,本文と同じA4サイズに縮小コピーなどして収めるようにします。付録が複数ある場合には連番(付録1,付録2.....)をつけます。付録は必ず本文中で参照されている(たとえば「〜については付録1を参照」と書いてある)ことが必要です。3)謝辞その他研究を行うにあたってとくにお世話になった人,協力してくれた人がいる場合にはその名前を記して感謝の意を表明します。実験や調査の協力者,インタビューの対象者,指導教員でないのに指導や資料提供をしてくれた先生などがそれにあたります。指導教員は研究指導するのが当たり前ですから指導教員への謝辞は必要ありません(これは先生によって考え方がいろいろあるようですが)。卒論の執筆や印刷について卒論の提出日は毎年2月末としていますが,12月くらいの時期ですでに書ける部分がたくさんあるはずですので,データの分析などを進めるかたわらどんどん書いていかないと間に合いません。また,書いてみてはじめて文献の不足だとか調べ忘れていたことがあきらかになってくるものです。締め切り直前に書けばよいと思わないこと。それからプリンターは卒論の印刷時には高い確率で故障したり紙づまりを起こします(プリンターが日頃の恨みを晴らす日)。印刷にも十分な時間的余裕をみるようにしてください。卒業論文の書き方 おわり 帯広畜産大学心理学研究室へ |