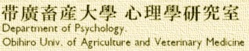
北海道医療大学看護福祉学部紀要 No.6(1999),pp59-68
講義における出席確認と出席の維持
~出席確認なしでも学生が出席する講義とは~
北海道医療大学・基礎臨床心理学講座
講師 渡邊芳之
University Lecture Classes ; Keeping student's attendance without roll-call
Yoshiyuki Watanabe,
Department of Psychology, Health Sciences Univ. of Hokkaido
Abstract: 138 students filled the questionnaire concerning their attendance at university classes. Most students (87.1%) attend some classes regularly without being called the roll. Moreover, almost all students (93.6%) would attend some classes currently with roll-call, if the lecturers no longer called the roll. Considering the student's questionnaire descriptions, it is suggested that the lecture classes can maintain their student's regular attendance without roll-call, when they evoke sufficient interest from the students, and/or when students suppose their academic achievements to rely heavily on their regular attendance. Some related issues on keeping student's attendance are also discussed.
Keywords: university classes, student's attendance, roll-call
1.問題
講義で出席確認を行なうかどうかについては,大学教員の中にもさまざまな考え方がある.まったく確認を行なわないし,学生が出席しないことについてもあまり気にしない人もいれば,出席の維持に非常に興味があって厳しい出席確認をする人もある.私自身はほとんど出席確認をしない教員であるけれども,出席確認をすべきかどうか,出席確認にはどのような効果があり問題点があるのか,といったことには以前から関心を持ってきた.本稿ではそうした問題について,出席確認に関する学生アンケートの結果などもふまえながら検討してみたい.
大学設置基準などに基づき,大学は講義科目の単位取得に出席の基準を定めている.単位を取得するためには講義に一定の割合で(本学ならば7割以上)(注1)出席した上で,試験などで一定の成績を収めると単位を取得することができる.講義によって教員から一定の知識や技術の移転を受けるためには,講義を聴講する必要があるからである.講義に出なくても知識や技術が修得できるなら講義の必要はないし,出席しても修得できないなら講義の内容か学生の能力に問題がある.一般には,大学の講義は入試によって一定の知的能力を保証された学生に対して,聴講しなければ修得できず,聴講すれば修得できる水準の内容で開講されることを前提とするので,出席することと知識技術の修得が連動するはずであり,したがって一定の出席が求められるのである.
しかし,このことがそのまま講義での出席確認に結びつくわけではない.出席確認しなくても学生が一定の割合で出席してくるならば,出席確認しなくても出席基準は達成される.多くの講義が出席確認を行なうのは,出席確認しなければ学生が出席せず,その結果出席しない学生の知識技術の修得が不十分になると,教員が認識しているからである(学生の側の認識については後で詳しく論ずる).この点で,講義で出席確認を行なうときは,それを行なわなければ学生の出席が維持できない,ということを前提としているといえるだろう.
最近の大学教育では学生が出席しないことがこれまでになく問題視されており,このことが大学での出席確認が一般化してきた原因であろう(注2).しかし,本当に学生は出席を取らない講義には出席しないのだろうか.また,学生は講義での出席確認をどのように感じ,評価しているのだろうか.そこで,学生に対してアンケート調査を行ない,履修している講義での出席確認の実態を把握するとともに,講義への出席と出席確認の関係について実態データや学生の意見を集めることにした.
2.調査の方法と対象
1 質問紙
調査は質問紙形式で行なった.質問紙の構成は以下の通りである.
1) 対象者の学年,学科専攻.
2) 現在履修している講義数,そのうち出席確認しているものの数.
3) 出席をとらないのに6割以上出席している講義はあるか,あるならその数.それらに出席している理由(自由記述).
4) 現在出席確認している講義のうち,出席確認しなくなっても6割以上出席すると思うものはあるか,あるならその数.それらに出席するであろう理由(自由記述).
5) 現在「おもしろい,興味がわく」と思える講義はあるか,あるならその数.それらのうち出席確認している講義の数.
6) 講義での出席確認はした方がよいと思うか.その理由(自由記述).
7) 出席確認についての意見(自由記述)
2 対象者
対象者は北海道医療大学看護福祉学部の「心理学�」(1999年1月12日火曜)に出席していた学生81名(58.3%),「臨床心理アセスメント�」(1999年1月13日水曜)に出席していた学生58名(41.7%)の計139名である.対象者の学年は1年生71名(51.1%),2年生47名(33.8%),編入3年生21名(15.1%),学科専攻は看護学科25名(18.0%),医療福祉専攻28名(20.1%),臨床心理専攻86名(61.9%)である(カッコ内は全体との比.性別及び年齢については調査の趣旨と関係ないので尋ねなかった).
3.結果
調査結果は,量的なものに関しては統計ソフトを用いて処理し,自由記述に関しては記述を内容ごとに整理分類した.結果の一般化が目的ではなく母集団の推定が必要ないためサンプリングもしていないので,統計的検定などは行なわない.また,履修科目数などの数はあくまでも本人の記述をそのまま用い,一見して事実と明らかに違う記述をしている場合(注3)も特に訂正,削除などは行なわなかった.
1 出席確認の比率
対象者が履修している講義(実習を除く)の科目数は平均10.6科目(最小値4,最大値17)であり,そのうち毎回出席確認している科目数は平均5.8科目(最小値1,最大値17)であった.履修講義数のうち出席確認する科目が占める割合を対象者ごとに計算したところ平均51.5%であった.対象者が履修している科目の約半数が出席確認を行なっていることがわかる.
2 出席確認しなくても出席している講義
対象者のうち出席確認しなくても6割以上出席している講義があると答えた人は121名(87.1%),そうした講義の数は平均3.8科目(最小値0,最大値16)であった.出席確認しない科目のうちそうした科目が占める割合を対象者ごとに算出したところ,平均64.6%であった.大多数の対象者が出席を取らない講義のいくつかに,ある程度継続して出席していることがわかる.
出席をとらなくても出席する講義がある人にその理由として自由記述してもらった結果を分類し,それぞれの数を示したのが表1の上段である(複数記述されている場合は内容ごとに分けたので,件数は対象者数を超える).もっとも多いのは「授業料がもったいない,講義をさぼることが不愉快,さぼれない性格である」といった経済・哲学・性格的理由(23.0%)だが,あとは講義内容に関するもの,つまり「講義が面白い,興味が持てる」(21.6%),「出席しないと講義内容が理解できない,テストでよい点を取れない」(18.8%),「講義内容が有意義,あとで自分の役にたつ,知識が得られる」
(13.6%)などの理由が続く.
 これらのことから,学生のある部分は出席確認しなくても自分の「人生哲学」から出席するし,そうでない学生も講義に面白さや価値を見出せたり講義に出席しないと内容が理解できないと感じる場合には,出席確認がなくても出席することが多いということがわかる.
これらのことから,学生のある部分は出席確認しなくても自分の「人生哲学」から出席するし,そうでない学生も講義に面白さや価値を見出せたり講義に出席しないと内容が理解できないと感じる場合には,出席確認がなくても出席することが多いということがわかる.
3 出席確認しなくなっても出席する講義
一方,現在出席確認をしている講義のうち,もし出席を取らなくなっても6割以上出席すると思う科目があると答えた対象者は131名で,全体の93.6%を占めた.そうした科目の数は平均4.7科目(最小値1,最大値17)で,出席確認科目のうちそうしたものが占める割合は平均63.1%であった.
「出席確認をやめても出席する理由」について自由記述してもらった結果を,前述の「出席確認しなくても出る理由」と同じ分類を施して表1の下段に示す.ここでは「講義が面白い,興味がもてる」という理由がもっとも多く(35.7%),以下「講義が有意義,自分の役にたつ」(25.8%),「出席しないと理解できない」(21.4%)が続く.
これらのことから,現在出席確認をしている講義でも,内容が面白く,意義深いと感じられたり,出席しないと理解できないと感じさせるような講義の場合,多くの学生は出席確認がなくなっても出席すると考えていることがわかる.
4 おもしろい講義はあるか
対象者の講義への興味度を探るために「現在履修している講義のうち面白い,興味がわくと思えるものはあるか」とたずねた項目では,133名(96.4%)の学生が「ある」と答えており,その科目数は平均3.6科目(最小値1,最大値14)であった.対象者ごとに履修科目全体の中でそうした講義が占める割合を算出したところ,平均32.4%であった.また,そうした講義のうち出席確認をしている比率の平均は57.8%であり,全体の傾向と差はなかった.
これらの結果から,学生の大多数には面白い,興味がわくと思える講義があり,その割合はおよそ3割程度であること,興味を持つかどうかとその講義が出席確認しているかどうかとの間にはめだった関係はないことがわかる.

5 出席確認への意見
「講義で出席確認をした方がよいか,しない方がよいか」という質問に対して,した方がよいと答えたのは9名(11.0%),しない方がよいと答えたのが59名(42.4%),わからない,どちらでもよいと答えたのが69名(49.6%)であった.学生の半数以上が出席確認について意見を持っており,そのうちの多数が否定的な意見であることがわかる.
その理由について自由記述してもらったところ,「出席確認した方がよい理由」については「出席してないのに単位が取れるのはズルイ」といった意見しか見られず,出席確認が学習を促進するというような意見はなかった.また記述数自体も非常に少なかった.いっぽう,「確認しない方がよい理由」については多くの記述が得られた.その分類結果を表2に示す.もっとも多かったのは「勉強するもしないも本人の責任」,「大学生なのだから強制しないで本人の意志に任せよ」といった「学生の自主性を尊重せよ」という意見(24.0%)だった.以下,「聴く気のない学生を強制的に出席させると私語や途中退出などが増えて聴きたい学生に迷惑」(22.7%),「聴く気のないものを強制的に出席させても無駄」(13.3%),「出席確認しなくても講義が面白ければ自然と出席する」(9.3%),「教員も出席に頼らず講義改善に努力すべき」(9.3%)などが続く.
講義での出席確認一般についての意見を自由記述してもらった結果を見ると,「つまらない講義,わけのわからない講義ほど出席確認が厳しい」,「まったく意義の感じられない講義に強制的に出席させれているのは苦痛」といった意見とともに,「大人数の講義で毎回点呼する教員がいる,時間の無駄だ」といった出席確認方法の問題点を指摘する意見も多かった.一方で「好きな講義では出席確認も励みになる」という意見も複数あった.出席確認が苦痛や反感の原因になるのはとくに講義に興味を持てない時であることがわかる.
4.考察
以上の結果から,出席確認しなくても多くの学生がきちんと出席しているような講義がかなりの割合で存在するし,現在出席確認していても,学生の出席が出席確認によって維持されているわけではない講義も多いことが示唆された.そして,出席確認が行なわれない場合,講義に面白さ,意義深さが感じられることや,出席しないと理解できないと感じられることなど,講義そのものの内容によって出席が維持されているケースが多いこともわかった.
これらの結果をふまえて,出席確認しなくても学生が出席する講義はどのような要因によって支えられるのか,あるいは,どのような講義において出席を取らないと学生が出席しなくなるのかについて考察する.
1 講義の意義が感じられること
出席を取らずに出席を維持するには,まず学生がその講義の内容に一定の意義を感じることが必要である.各科目の単位を認定されることは卒業の条件になるだけでなく,本学のような養成校では国試受験資格など将来の進路に直結することが多いため,学生は単位を取らねばならない.しかし,その講義の内容に意義を感じられない場合,学生の目的は聴講して知識や技術を身につけることより,単位を獲得することだけに特化する.したがって「ムダな講義」に毎回出席するよりは,試験対策だけを行なって単位を獲得するようになるから,出席確認してそれを単位取得の条件にしない限り出席しなくなるのである.
本学のような養成系大学では,学生の大半が特定の職業への就職や資格の取得を目的に入学してくる.学生が講義内容に意義を見出し自発的に出席してくるためには,その講義内容が将来の業務に直結したり,将来の業務に重要な意味を持つこと,あるいは資格試験への合格のために必要な内容であることを学生にはっきりと示し,理解させる必要があるし,教員はそれに見合った講義内容と水準を維持しなければならない.
その点で,一部の医歯薬系学部のように学生の目標が(ときには学部の教育目標も)国家試験合格だけであり,国家試験に合格するためには実は大学の講義に出席するよりも予備校などに通ったり,自宅で受験対策する方が有効であることが暗黙の常識になっているような場合には,一部の実習などを除いて,大学の講義は国試受験資格に必要な単位を獲得するため以外の意味を持たなくなる.まして定期試験の成績も講義出席より直前の暗記量によって定まるようであれば(この問題については後で改めて論ずる)講義に出席する意義はまったくなくなる.したがって厳しい出席確認や出席点の成績化を行なわなければ学生が出席しなくなるのは当然である.こうした状態が大学として健全であるとは思えない.
2 講義の「おもしろさ,興味深さ」
学生が講義におもしろさや興味深さを感じることも,自発的な出席を維持する上で重要なことである.一般に講義のおもしろさという場合には,「ユーモアを交えた講義をしろ」とか「学生の視点までさがって話せ」など,講義技術の面ばかりが問題にされるため,時には「講義はエンタテインメントではない」「学問はおもしろおかしいことばかりではない」といった反発が生じる.たしかに学生の考えかたや趣味に合せたり,学生が興味を持ちやすい話題から導入するといった技術も講義の面白さの一要因だろう.しかし,学生が講義におもしろさを感じる主要な要因はそうした講義技術ではなく講義の内容そのものであり,端的にいえば「聴講して理解でき,自分の知識や技術が向上すること」がおもしろさの感覚を生み出していると考えるべきである.その点で,学生が学ぶ喜び,理解する喜びなどの知的興奮を得られる講義が,おもしろい講義であるといえる.
この点で,「出席しなくても理解できる内容」や「出席しても理解できない内容」ではなく,「出席しないと理解できないが,出席すれば理解できる内容」の講義に学生は知的興奮を感じるし,自発的に出席する傾向が高まるだろう.そうした講義を行なうためには,学生の水準と講義の水準を注意深くマッチングすることが必要である(注4).
 学生の水準と講義の水準との関係を図1に示す.講義の水準が学生の水準より低い場合(第1領域)では,学生は既知の知識技術を講義されることになり,また講義内容の理解に努力を要さない.この場合学生は講義内容に知的興奮を覚えないし,出席しなくても学習が達成できるため出席する意義は低まる.いっぽう,講義の水準が学生の水準より高すぎる場合(第3領域)では,学生は聴講しても理解できないので知的興奮は感じないし,講義に出席する意義もない.講義の水準が学生のそれをわずかに上回るような場合(第2領域),学生は講義を聴講するとともに一定の努力をすることで講義内容を理解できる.この場合だけが知的興奮を生み,講義への自発的出席を導く.
学生の水準と講義の水準との関係を図1に示す.講義の水準が学生の水準より低い場合(第1領域)では,学生は既知の知識技術を講義されることになり,また講義内容の理解に努力を要さない.この場合学生は講義内容に知的興奮を覚えないし,出席しなくても学習が達成できるため出席する意義は低まる.いっぽう,講義の水準が学生の水準より高すぎる場合(第3領域)では,学生は聴講しても理解できないので知的興奮は感じないし,講義に出席する意義もない.講義の水準が学生のそれをわずかに上回るような場合(第2領域),学生は講義を聴講するとともに一定の努力をすることで講義内容を理解できる.この場合だけが知的興奮を生み,講義への自発的出席を導く.
学生の水準と講義の水準をマッチングさせ,多くの学生を第2領域に導入するためには,講義計画の段階で学生の水準を注意深くアセスメントし,講義計画に反映させる必要がある.もちろん学生の水準には個人差があるから,講義の水準をいかに吟味しようと第1領域,第3領域の学生を完全になくすことはできない.また,第3領域の学生を減らすために講義内容の水準を下げるとカリキュラム全体から見てその講義に求められる知識技術の水準を達成できない場合も生じる.この場合はカリキュラムとの関係を重視すべきだろう.
講義内容がカリキュラムの趣旨にてらして適切であれば,第1領域の学生は必要な知識技術をすでに身につけているわけだから問題ないし,この場合講義への出席も必要ない.講義の水準を低下させずに第3領域の学生を第2領域に引き上げる必要が生じた時に初めて,教員の講義技術,講義方法の吟味が重要になってくるだろう.それらを考慮しても第3領域に留まる学生がいる場合には,カリキュラム上必要な知識技術を達成する水準にないわけだから再履修を課したり(注5)進路変更などの指導を行なう必要が生じる.
3 出席しないと理解できない,単位が取れない
学生がその講義に単位取得以上の意義や興味を感じることができなくても,その科目の単位取得には講義内容を理解する必要があり,かつ出席しなければその「理解」が達成できないことがわかっていれば,出席確認しなくても学生は出席する.それには,講義が明確な達成目標を示すとともに,毎回の講義がその達成目標と系統的に結びついていることを学生にはっきり理解させる必要がある.そして,適切かつ厳密な試験によって学生の達成水準を評価することも必要である.つまり,「出席しないと理解できない(できなそうな)講義」を行ない「出席しないと合格できない(できなそうな)試験」を実施することで,出席を維持することができる.
この点から見てもっとも望ましくないのが,「教員自身も何を教えたらいいのか,何を教えているのかわからない講義」である.こうした講義は伝統的に大学で教えられてきた科目よりも,社会福祉や臨床心理といった,最近大学教育にとりいれられた領域に多いように思われる.こうした領域では大学教育での達成目標や教育内容・手段についてまだ一般的な認識が確立していない上に,教員の多くは現場の出身で,自分が担当する科目について大学で教育された経験(注6)も,教育した経験も少ない.この場合講義で明確な達成目標を示すことは難しいし,達成目標が明確にならない以上試験による評価も無効であったり,恣意的になったりする(注7).また,学生から見れば出ても出なくても変わらない講義となって,出席するかどうかは個人の嗜好に任されることになる.この場合,出席確認を行なわなければ出席が維持できないだけでなく,出席点を用いなければ成績評価もできなくなるのである.
このように講義の達成目標が不明確になり,結果として成績評価の基準が不在になることには,3つのパターンが考えられる.第1は,その講義が扱っているものが本来明確な達成目標を立てたり,それで評価したりすることになじまない場合である.典型的なものは芸術表現であり,これらは大学教育のようなシステムよりも徒弟制度になじむ(注8).とくに心理療法など臨床心理学の一部にはこうした傾向が強く,これまではおよそ徒弟制度に近い方法で教育されることが多かったため,客観的には明確な達成目標も評価基準も定められないことが多い.それを無理に大学教育に組込むから,出席評価や受講態度評価などの「参加点」で評価するしかない場面が増える.
第2は,その講義が扱う領域自体は達成目標を明確にし評価基準を設けることが可能なのだが,まだそれが実現されていない場合である.臨床心理領域の大半や,社会福祉領域がそれにあたるだろう.本来ならばそうしたことがある程度確立してから大学教育に本格的に取り入れられるべき領域だったのだが,社会的要請などの面からなしくずし的に導入され,教員も何をどう教えていいかわからないまま試行錯誤している,というものである.これらは今後徐々に進歩して達成目標や評価基準が確立されることが期待できる.
第3は,その講義が扱う領域は達成目標も評価基準も明確にできるもので,かつ一般的な同意も成立しているが,担当する教員がそれを行なっていない場合である.これは教員の努力不足,あるいは教員の能力や適性の問題に起因するだろう.以上上げた3つのパターンのうち,実際には第3のタイプが一番多いと考えられる.
また,達成目標は明確であっても,各回の講義がそれと系統的に結びついていない場合にも,出席の維持は難しくなる.毎回の講義がどれも達成目標ときちんと関連しており,続けて出席することが累加的に全体的達成を保証するのでなければ,学生は出席しない.達成目標が講義に出席することとは無関係であるような場合はなおさらである.テキストを指定して毎回それを朗読するだけのような講義では,出席しなくても一人でテキストを熟読すれば目標は達成できる.テキストを用いる講義では,テキストを読むだけでは理解が不十分な部分を補足したり,テキスト外の関連知識を提供する必要があり,またその内容が全体の達成目標と明確に関連していなければ,出席を促進することはできない.
同様に,試験などによる達成評価が講義内容ときちんと結びついていないような場合にも,学生は出席しなくなる.講義自体は明確な達成目標に基づいたものであっても,試験の内容が講義内容をきちんと理解していなくても解答できるものであったり,直前にテキストを暗記すれば解答できるようなものであったりするなら,単位の獲得は講義への出席より「試験対策」に依存するから,単位だけを必要とする学生にとっては講義には出席しないでその時間を有効に使い,直前に試験対策だけ行なう方が合理的である.それ以前に,その試験内容,試験によって確認される達成内容がカリキュラムにてらして適切なものであり,かつそれが「試験対策」だけによって達成されるのであれば,そもそも講義を行なうこと自体が無意味である.これはやはり医歯薬系学部の講義でよく見られることであり,ここでも出席確認しなければ誰も出席しなくなる.
4 出席確認の積極的問題点
これまで考えてきたように,出席確認を行なわないと出席が維持できない,かつ/または出席点を考慮しないと成績評価ができないような講義は,それ自体にいくつかの問題を抱えている場合が多い.最近の大学教育で学生の出席維持が問題になっているとすれば,現在の大学教育全体が先に述べた問題点のいくつか,あるいはすべてを抱えていると考えることもできる.いずれにしても,出席を維持するためには講義内容の改善,調整が先決であり,出席確認を厳しくして強制的に出席させることは本末転倒である.
それだけでなく,出席確認によって出席を維持することは,それ自体が学生の学習や目標達成を阻害する「副作用」を有する.第1に,出席確認を行なうことでほんらい講義に興味がなく,聞く気のない学生を強制的に出席させることになるので,講義に集中できない学生の私語が増えて,まじめに受講している学生の学習の妨げになる.たとえば本学の臨床心理系講義では「心理専攻以外の学生の私語が多くて困る」「心理専攻だけのクラスに再編成してほしい」という苦情が例年学生から寄せられている.また,出席確認の時だけ教室に入り,それが終わると教室から出るというような学生が増えて,途中入室,途中退出も問題となる(注9).このように出席確認が講義の受講環境を悪化させ,興味をもって受講する学生の学習権を侵害している場合があることは,先に述べた調査結果(表1)からも明らかである.また,強制的に出席させられた学生はもとよりまじめに受講することも,学習が進展することもないのだから,全体の学習達成はむしろ低下する.
第2に,もともと講義に興味をもって受講している学生に対する,出席確認のマイナスの効果についても考慮しなければならない.まず,内発的動機づけの理論では本人の意志や興味(内発的動機づけ)によって生じている行動に対して報酬や賞賛など(外発的動機づけ)を与えることは,かえって内発的動機づけを低下させ,行動の自発性を損うとされる.講義の場合も,ほんらい自身の興味や目的意識などの内発的動機づけに基づいて受講している学生にたいして出席確認などの外発的動機づけを与えることで,その学生の学習への意欲を低下させる危険がある.調査の自由記述解答の中にも「講義内容に興味を持って自発的に出席しているのに,毎回出席確認されるとやる気がそがれる」といった意見がみられた.
また,オペラント条件づけの原理から考えても,出席確認による出席の維持は本人にとって報酬となるものによる行動の維持(正の強化)ではなく,嫌悪刺激(この場合は失格,落第などの結果)をその行動によって回避できること(負の強化)による行動維持である.負の強化により維持される行動は,一般に本人にとって不愉快で自発性をともなわず,また消去抵抗(注10)が弱いので強化がなくなると(この場合は出席を取らなくなると)すぐに消去する.つまり,出席確認によって維持されている出席は本人にとって不本意で不快であり,確認しなくなれば即座に出席しなくなってしまう恐れがある.調査結果ではそうした傾向は明らかになっていないが,自由記述に「おもしろい講義で出席を取られるのはまだがまんできるが,くだらない講義に出席で縛られるのは非常に不愉快」というような否定的な感情反応が多くみられることは重要である.
このような問題点を考えると,やはり講義への出席は出席確認とは違う方法,すなわち講義内容改善や適切な成績評価によって学生の自発的出席を促す方法で維持されるべきといえる.
5 関連するいくつかの問題
1)受講態度の評価
講義内容以外で学生の出席を維持したり,評価したりする方法として,「受講態度の評価」がある.単に出席を確認するだけだと,出てくるだけで学ばない.まじめに受講し,参加しているかを評価すべきだ,という考え方である.一般には出席評価より踏込んだ積極的な方法と考えられているが,最大の問題は受講態度が教員の主観によって評価されていることである.受講態度の良否が明確に基準化され,客観的に評価されていることはまずなく,極端な場合は教員の「好み」に合う学生が高く評価され,そうでない学生は低く評価されるということが起きる.受講態度評価を有意義なものにするには,評価が的確に行いうる程度の人数に受講者を限定するとともに,担当教員一人だけなく複数の教員等が受講態度を観察し,全員の評価を平均するような間主観的(注11)な評価が必要であろう(注12).
2)参加型講義
また最近では「参加型」の講義などと称して,教員がはっきりした達成目標を示すことをせず,一定の議論テーマなどを提示して学生が参加し,議論を深めていくというような講義がもてはやされている.こうした講義はいっけん本稿の問題と無関係なように見えるがそうではない.第1に,そうした講義も「参加することによって学生に何を学ばせるか」という達成目標をもつはずであり,それを示さなければ単に「参加することに意義がある」というものになって学生の興味は惹かないし,出席や参加は維持できないから,結局参加の確認や評価は出席確認と同じことになる.第2に,そうした講義も大学教育の枠内では必ず成績評価を行なわなければならない.しかし,達成目標がなければ達成評価はできないから結果として出席確認や受講(参加)態度の主観的な評価に頼らざるを得なくなる.問題はまったく同じである.
3)小テストの実施
出席確認ではなく,毎回の講義の中で小テストなどを行なうことで出席を維持している例がある.こうした方法は単なる出席確認とは多少事情が異なる.現在の講義と評価のシステムでは,15回から30回の講義を聞いた後で試験によって成績評価されることが多い.このシステムの問題点は,学生は毎回の講義において自分の理解度を確認するようなフィードバックを受けない,ということである.自分が理解できているのかいないのか,自分の理解は正しいのかといったことが確認されないまま続けて講義に出続けるため,途中で理解が躓いても放置されるし,講義受講や理解への意欲が維持されにくい.
こうした問題を解決するためには,毎回の講義で学生の理解度を適切に把握し,理解していない学生には復習による理解を促すことが役立つ.その点で毎回の講義で小テストなどを行なうことは有効である.ただし,この意味で小テストが有効なのは,テストの結果(自分の理解度)ができるだけ早く,できればその場で学生にフィードバックされる場合だけである.また,その場合には学生へのフィードバックだけが重要であるから,小テストを出席確認に振替えたり,成績を講義の成績評価に反映させなくても,テストを行なうだけで出席維持の効果がある.
反対に,毎回小テストを行ない教員が回収するがその結果がすぐに学生に知らされなかったり,「課題」などと称しても単なる感想であって,講義の理解度などがそこから把握されない場合は出席維持の効果はなく,単なる「出席票の変形」の意味しかなかったり,ときには学生に不要な負担を強いるだけになる.小テストが出席確認以上の効果を上げることができるのは,一定の条件が整った時だけであり,いうまでもないがそうした効果のある小テスト実施は教員にかなり大きな負担を強いる.
6 まとめ
大学教育の目的は一定の知識や技術を教員から学生へと移転することである.そうした知識の移転を受けること(学習)が一般に出席に依存するということ以外に,出席を強要する根拠はない.もし講義に出席しなくてもそうした知識や技術を達成できる学生がいるなら,その学生は講義に出てくる必要はないのだし,逆に講義に皆勤で出席していても知識技術が達成できないのであれば,出席には意味がない.講義への出席は,それが一定の知識技術の達成と結びつく時に初めて必要となるのであり,出なくてもわかる講義に出る必要はないし,出てもわからない講義に出てもしかたがない.
しかし教員の立場からみれば,学生が出席してくれなければ講義は成立しないし,とくに出なくてもわかる講義や出てもわからない講義,出てもしかたのない講義ほど適切な成績評価ができないから,「評価による学生の序列化」を行なうために出席点で評価する必要が生じる.出席確認やそれによる評価は学生の学習促進というよりむしろ,学生が出てきてくれないと困る,出席でしか評価できないという教員の都合によって実施されているのである.
実際にはその大学や学部のカリキュラムや講義が出席を維持できないレベルのものであることをまったく反省しないで,「いまの学生は強制しないとサボる」「学生が自発的に講義に興味をもつなどということはない」などと学生にその責任をおわせ,厳しい出席評価によって学生を強制的に出席させるようなことでは,大学教育は堕落するばかりである.自由記述の中にも「自分の講義に自信のない教員ほど出席が厳しいのでは」「出席とらないと誰も来ないのが怖いのでは」と,教員の本音をきちんと見抜いている意見がたくさんあった.学生は講義から教員の実力をきちんと判断している.小学校や中学校のように教員と生徒との発達段階が明らかに異なっている場合ならいざ知らず,大学では教員も学生も「おとな」であり,教員よりも学生の知的水準が高いこと,教員のレベルの低さが学生に見透かされていることは,いくらでもありうる(注13).
学生を教室に呼び戻すために必要なのは出席確認などの姑息な方法ではなく,学生がそこに価値を見出せるおもしろくて興味のもてる講義を展開するように教員が努力することだけである.それを理想論と退け,学生のレベルが低いだの,最近の学生は意欲がないだのと嘆き続けるだけなら,大学教員という職業を今後も続けることにどんな夢がもてるだろうか.
注
1)北海道医療大学看護福祉学部履修規定(平成9年4月1日施行),学生便覧98,176-178,1998.
ただし,実際には多くの講義で「6割以上出席」という基準が運用されている.したがって以下の調査などでも「6割以上出席すること」を正常な出席の基準と考える.
2)私が大学生の頃(1980年代初頭)には,出席確認する講義は体育実技や一部の基礎教養科目など,ごくわずかだった.同じ大学で私が非常勤講師として勤務していた頃(1990年代初頭)には出席確認する科目がかなり増えていた.
3)出席確認していない私の講義の出席者で「履修科目は10科目,そのうち出席確認しているもの10科目」などと答えている場合などがこれにあたる.
4)ここでいう「学生の水準」とは学生の知的水準,予備知識,それまでの学習体験,学習内容などを総合した概念として用いる.
5)出席したのに講義が理解できず必要な知識や技術を達成できなかった学生には,講義自体を再履修する必要と権利がある.その点で本学の仮進級制度のように不合格者に再試験を繰り返し,再履修なしで合格させてしまうような制度には問題がある.
6)自分が学校で教わった経験のある内容について教育するのは比較的たやすく,人から教わらず自分で開拓した内容について(とくに自分の専門分野について)教育するのは意外と難しいということは,教育に携わるものなら誰でも経験していることだろう.
7)こうした講義の多くは,教員が現場時代に体験したエピソードや,職業哲学のようなものをつれづれに講演的に話すものになる.この場合,教員が話したエピソードをどれだけ記憶しているかとか,教員の哲学にどれだけ共鳴したかなどを試験して評価するなどということはナンセンスであろう.こうした講義はレポートを課すことが多いが,その内容はおもに「講義への感想」であって講義に出席していなくても書けるし,感想の内容を評価するわけにもいかない.したがって,レポートは提出したかどうかだけが評価の基準となり,出席確認と同じ意味になる.
8)教養科目などで芸術が扱われる場合に芸術そのものを教育するのではなく,芸術が歴史学や文化人類学などの視点から扱われることが多いのはそのためだろう.
9)だからといって私語を見つけては減点したり,講義中に教室の出入口を施鍵したりしてもイタチゴッコになるだけだし,講義自体のそもそもの目的が見失われてしまう.
10)環境からの強化によって維持されている行動が,強化がなくなってもしばらくの間持続すること.辛抱強い行動,継続的な努力などは消去抵抗の強さの現われである.
11)間主観性とは,複数の人による主観的観察の間に共通性が認識されることによって,それらの観察の妥当性が社会的に保証されていることである.これまで漠然と「客観性」と考えられていたことの主要な要素のひとつ.
12)こうしたことが現在の大学で現実的でないことはいうまでもなく,受講態度の評価を主観的でなく行なうことは実質的に不可能である.
13)本学のような「低偏差値大学」ではその心配はない,などと考えることは妥当ではない.学業成績と対人的な知能や「かしこさ」は一般にそれほど相関しない.また,世間一般の価値観から見れば「低偏差値大学」では学生の知的水準だけでなく教員のそれも低いと考えられるだろうし,学生もそれを想定していると考えるのが順当である.
ホームページに戻る
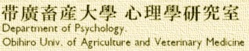
 これらのことから,学生のある部分は出席確認しなくても自分の「人生哲学」から出席するし,そうでない学生も講義に面白さや価値を見出せたり講義に出席しないと内容が理解できないと感じる場合には,出席確認がなくても出席することが多いということがわかる.
これらのことから,学生のある部分は出席確認しなくても自分の「人生哲学」から出席するし,そうでない学生も講義に面白さや価値を見出せたり講義に出席しないと内容が理解できないと感じる場合には,出席確認がなくても出席することが多いということがわかる.

 学生の水準と講義の水準との関係を図1に示す.講義の水準が学生の水準より低い場合(第1領域)では,学生は既知の知識技術を講義されることになり,また講義内容の理解に努力を要さない.この場合学生は講義内容に知的興奮を覚えないし,出席しなくても学習が達成できるため出席する意義は低まる.いっぽう,講義の水準が学生の水準より高すぎる場合(第3領域)では,学生は聴講しても理解できないので知的興奮は感じないし,講義に出席する意義もない.講義の水準が学生のそれをわずかに上回るような場合(第2領域),学生は講義を聴講するとともに一定の努力をすることで講義内容を理解できる.この場合だけが知的興奮を生み,講義への自発的出席を導く.
学生の水準と講義の水準との関係を図1に示す.講義の水準が学生の水準より低い場合(第1領域)では,学生は既知の知識技術を講義されることになり,また講義内容の理解に努力を要さない.この場合学生は講義内容に知的興奮を覚えないし,出席しなくても学習が達成できるため出席する意義は低まる.いっぽう,講義の水準が学生の水準より高すぎる場合(第3領域)では,学生は聴講しても理解できないので知的興奮は感じないし,講義に出席する意義もない.講義の水準が学生のそれをわずかに上回るような場合(第2領域),学生は講義を聴講するとともに一定の努力をすることで講義内容を理解できる.この場合だけが知的興奮を生み,講義への自発的出席を導く.